アングロサクソン型資本主義が失敗したと安易に決めつけるのは、ポピュリスト的な議論としては分かりやすいだろうが、本質を突いていない。
今回の金融危機を、規制緩和や市場の失敗のみに責めを帰することはできない。ウォール街の金融機関が暴走していたことは疑いないが、これと両輪をなすのが、むしろ、当局の失敗、政治の失敗である。
たとえば、震源地の一角を担った政府系住宅金融機関(GSE)のファニーメイとフレディマックは、米国金融界でもっとも規制が強い分野であり、持ち家比率を向上させるという政策意図を持って活動してきた。政治的な意図を持って銀行を経営し、社会政策としてより広い層へ融資を拡大することがもたらす弊害は、米国のみならず、最近ではわが国の某都でも見られたのではないか。
住宅バブルを無視して低金利政策を続けてきたFRBの責任も小さくないだろう。政策の失敗が、中国や産油国による外貨準備の積み立てを増やすというグローバルな図式によって、金融危機に火をつけるきっかけとなった。リーマンを破綻させたのが失敗だという声もあるが、それが引き金を引いたにせよ、バブルはもうはち切れんばかりに膨張していたことは間違いない。
グローバルな供給余力の拡大によってインフレが抑えられるという、過剰流動性を拡大させるマクロ経済的な議論がなされていたことも問題だったのだろう。政治的には国内の借り入れが拡大していっても、より自由な資本市場とアジア諸国の貯蓄によってそれがファイナンスされている限りは、消費を後押しするものとして歓迎されたのだろう。
グリーンスパン前FRB議長も近著で、その生業ゆえに高いレバレッジがかかっている金融機関がCDS(クレジットデフォルトスワップ)を通じてクレジットリスクを移転できることは、より低いレバレッジでも同等のROEを得られることから、経済の安定化にとって望ましい、とポジティブに述べていたそうだ。これは理屈では正しい。ただ、運用における監督が不在であったことがオフバランスでCDSを膨張させたことが、問題なのだろう。
銀行のバランスシートの健全化を目的として定められたバーゼルの自己資本規制が、結果として銀行の債務のオフバランス化を加速化させ、証券化、ストラクチャード投資、そしてCDSを通じたデフォルトリスクの縮小を招いたのは何とも皮肉なことかもしれない。
厳しい規制が金融危機を生まないと言い切れないのは、1990年代に日本や韓国が金融危機に陥ったことを見ても、分かるだろう。日本のバブル後の金融機関への公的資金注入がまるで成功例のように語られているが、当時は "too small, too late" と非難され、結局、循環的な景気回復によって不良債権処理が進んでいったことは、今朝の日経新聞「経済教室」で大村敬一早稲田教授が指摘する通りである。
金融における規制緩和がもたらしたメリットは、昨今のような金融危機下では、指摘することは容易ではない。しかし、過去30年間の未曾有の経済拡大は、資本市場が整備されたことや金融技術の発展によって、消費者や企業がより安い資本へアクセスすることができていなかったら、実現できただろうか?
「市場対規制」といった単純な図式ではなく「賢い規制」を模索することだ。金融と経済のバランスを正常化させる「新しい資本主義」を目指すときでもある。
日経新聞主幹の岡部氏による「主役なき時代の金融危機」(2008年10月20日朝刊)で述べられている上記の指摘に、まったく共感する。
現状の日本は、「相対的にマシ」なだけで、ちょっと前まではグローバル経済での劣等生とされていたことも、忘れてはいけない。まだまだ、規制緩和は進めなければならない。
上記の議論は、以下の文献を参考にしてまとめました:
Economist "Link by Link - A Short History of Modern Finance", Oct 16, 2008
同 "Capitalism at Bay", Oct 16, 2008
BusinessWeek "The Future of Kapitalism --- Forget Adam Smith, Whatever Works", Oct 16, 2008
日本経済新聞 経済教室 「資本注入で問題解決せず」(大村敬一教授)2008年10月20日日経シンポジウム オリックス宮内会長の基調講演

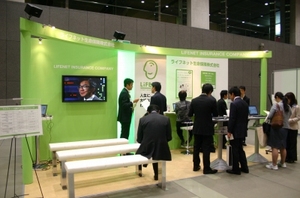

最近のコメント