本書はベストセラーとなった「ウェブ進化論」と同様、ウェブが切り拓く未来への期待とオプティミズムに満ちている。読者はまるで見晴らしのいい展望台から、新たな大陸を見渡す機会をはじめて与えられたような、すがすがしい読後感を覚える。
しかし、私が本書を読み終えて感じたのは、このようなすがすがしさだけではなかった。むしろ、大きな後悔と、焦りの気持にかられた。再び本書を開き、気になったページに折り目をつけながら、何度も何度も、本書を読み返さずにはいられなかった。
それは、「もうひとつの地球」と著者が呼ぶ新しいウェブ世界のスケールの大きさに圧倒されつつも、その表層しか理解していなかったことと、それゆえ同時代を生きる我々に等しく与えられた機会を十分に活かさずに、怠惰に毎日を過ごしてしまっていることへの後悔。そして、このままでは、梅田氏が提示するようなあたらしい生き方を実践することなく、何十年か何百年に一度しかない大きな波に乗り遅れてしまうかもしれない、そんな脅迫観念に近い焦りである。
前作の「ウェブ進化論」でも、ウェブ世界の本質は既に語られ尽されていたはずである。しかし、本書が私により深い気づきを誘発し、痛烈なメッセージを心に残したのは、「あなたはウェブ時代をどう生きるのか」と、何度となく私たちに迫りながら、ウェブ世界の本質について語っているからかもしれない。
■ 水や空気のようにウェブがそこに在ること
私はこれまで、インターネットを基軸とした「時代の大きな変わり目」「混沌として面白い時代」に生きているという時代認識を十分に持つことなく、毎日を過ごしてきた。
1976年に生まれ、いわゆる「ナナロク世代」に属する私は、大学入学とともにインターネットの世界に誘われ、社会人としての一歩を歩みはじめたときからデスクにはインターネットと電子メールが用意されていた。ブラウザーを通じて、リアルタイムに国境を越えて大量の情報にアクセスできる環境がそこにあった。コンサルティング会社ではじめて与えられた調査課題も、ネットで探し当てた西海岸のベンチャー企業にメールを打つことで解決できた。
私にとって、インターネットを使ってプロフェッショナルとしての知的な生活を生きることは、決してラグジュアリーではなく、デフォルト(基本仕様)なのである。ネットがなかった時代を懐かしく思い出し、そのありがたみを改めてかみしめるようなことはない。
英語で、take for granted という表現がある。何かが在ることを空気や水のように当たり前と感じ、ありがたみを感じていない状況である。私がウェブ世界に対して抱いている感覚は、この言葉によく表わされる。
徐々に進むネットの質的な変化に気がつくことなく、それは限界的な利便性の向上くらいにしか理解せず、新たなる地球の出現に気がついていなかったのは、ずっとネットともに社会人生活を営んできた、そんな背景があるのかも知れない。
■ 「脳を預けたら膨らんで戻ってくる感覚」
はてな創業者の近藤淳也氏は、ネットの本質は『知恵を預けると利子をつけて返してくれる銀行」である、と口癖のように語っているそうだ。梅田氏はこの考えをさらに推し進め、「脳を預けたらそれが膨らんで戻ってくるような感覚」、とも述べている。
私自身、数千人の読者が毎日訪れるブログという小さなコミュニティを持つ幸運を得て、これまで千件近いエントリーを書いてきた。しかし、近藤氏や梅田氏が述べるような、ブログを通じて大きな知的刺激を受けるような体験は、これまでしたことがなかった。
それは、読者の参加意欲やリテラシーに起因しているわけではない。むしろ、自分のブログは「MBA留学記」としてはじまったこともあり、比較的高い意欲と知性をもった読者層に恵まれていると思っている。本格的な双方向のプラットフォームとして活用できていないのは、私自身のブログに対する哲学(の欠如)が要因である。
いつからか、私はエントリーのテーマを選ぶ際に、読者の物議をかもさないような、差しさわりがないものを選ぶようになっていた。それは「当該テーマについては自分が他の人よりも詳しい」と考えるものか、きわめて個人的・日常的な話題に限られていた。「自分がその話題を語る資格があるか否か」を考えるあまり、自分が本当に疑問を持っているテーマをあえて取りあげ、ネットを通じてより知識を深めるといった態度は、ほとんど取っていなかった。
結局、ブログでは一方的にメッセージを発信するだけであり、積極的に対話を求める読者からのコメントには表敬的なお返事をするにとどめていた。これでは、前時代的な紙媒体の「ニュースレター」の域を超えていないのではないか。
そんな私も、ブログをきっかけとして時折起こる、いくつもの「奇跡」を体験していたはずだ。ブログなくして、自分の意見を不特定多数の人に聞いてもらい、あたらしい友人たちと出会い、書籍を出版して意見をより広く世に問うことはできなかった。それなのに、なぜブログやウェブの本当の力を、信じることができないのか?
■ 大企業とベンチャー、リアルとあっち、サイエンスとアートの「同時通訳」
ウェブ世界の覇権を握る存在として本書で何度となく引用されているグーグルは、「世界中のすべての情報を整理する」という、気が遠くなりそうな壮大なビジョンを描きながら、地に足が着いた営利企業として、群を抜く収益性と成長性を誇っている。
私は、その凄まじいビジネスモデルがこの世に生まれたのは、決して「奇跡」ではないと考えている。その圧倒的な技術思想と実装能力をmonetizeすることを可能ならしめたのは、世界から集まった優秀なエンジニア、自分の身の丈に留まらないビジョンを描くことを奨励する風土、そしてクライナーパーキンズに代表されるVCのような「大人のビジネスパーソン」たちが経営の暗黙知を伝え継ぎ、企業を永続的なものとする「儲けの仕組み」を夜を徹して考案するという、「シリコンバレー的な異質なるもの」の組み合わせではないか。
そして、この事象は、なぜ梅田氏の言説が現在の日本でこれほど広く支持されるか、ということとも共通する要素があると考えている。
梅田氏を同時代の思想リーダーの一人たらしめているのは、氏がシリコンバレーに身を置いて日々空気を感じながら誰よりも膨大な情報を摂取し、分析しつつ、それを未だにエスタブリッシュメントが君臨する日本社会の新旧勢力、誰にでも分かる平易な言葉を用いて、語っているからだと考える。すなわち、二つの異なる世界を流暢に「同時通訳」できるから、である。
敷衍すると、それは梅田氏自身が大企業やエスタブリッシュメントといった「リアルの地球」と「もうひとつの地球」の双方をよく知っているからだけではないのかもしれない。氏は数学やコンピューターといった「理系」の科目を愛しながらも、同じくらいに社会や制度、文化といった「文科系」の科目にも造詣が深い。また、歴史的な視座もあるから、より本質的な洞察力にたけている。だからこそ、分かりやすく読みやすく、同時に心に響く言葉でメッセージを発することができるのだろう。
最後にもう一つ理由を掲げるなら、梅田氏の言説には、若い世代に対する、父性に似た思いやりと愛情が感じられることがある。
もしかしたら、多くの若い梅田ファンは、ひたすら企業社会で猛烈サラリーマンとして生きた父親、自分たちの生きざまを100%には理解してくれない父親にどこか不満を感じているとともに、氏の言葉に、まるで自分の生き方に対して視座を与えてくれ、ときには厳しくその怠慢を叱咤し、ときには優しく包み込んでくれる、父親のようなものを感じているのかも知れない。
そしてそれもまた、「オトナ」と「若者」の世界の、同時通訳としての機能を果たしていることでもある。
■ 「こちらの世界」で満足している人たちにこそ、本書はある
本書を通じた氏の狙いのひとつは、優れた才能を持っていながら、日本の企業社会に適することができない人たちに対して、新しい生き方を提示することにある。それ自体はとても重要なことであるし、実現できたら、わが国の社会に大きなインパクトを与えよるだろう。
しかし私は同時に、いわゆる「こちらの世界」で心地よく生きてしまっている、ぬるま湯につかっている人たちに対しても、本書をきっかけに、この新しい世界に乗り出してみることを望む。
エスタブリッシュメントに属する人たちが、例えば法曹関係者が、中央官庁の官僚が、政治家が、あるいは大企業の中核を担っていくような人たちが、属する組織の巨大なリソースをもって、ウェブ的なるものを使いこなすようになれば、それは我が国にとって新しい道を切り開いてくれる気がするからだ。
■ 最後に、、、自分はどう変わるか?
本書を読んで、「ふーん」「へー」というつかの間の納得と、何らかの気持ちの高ぶりを覚えただけで終わってしまっては、梅田氏は本望ではないだろう。氏が望むのは、本書を手に取ることによって、一人、二人と、そこにある生の人生が変わることなのだから。
とすれば、私自身も、立派な読書感想文を書いたことで満足することなく、自分の日々の生活、生き方を変えていなければならない。
では、具体的にどのように変わることができるのだろう?
一言でいうと、「目の前にある大きな機会を、もっと積極的に活かすこと」である。
一つは、情報のインプットをより多様に広げること。いま、せいぜい目を通しているブログは5つくらいか。これを、50とか100に広げる。すべてを毎日読む必要はなく、興味を持ったものだけでいい。そして、自分の分野とできるだけ違うものも入れるようにする。関心を持ち続けるのは難しいかもしれないが、中に面白いものがひと月に一回あれば十分だろう。
もう一つは、アウトプットをより豊かなものにすること。ブログを、こちらが言いたいことを言う、一方通行なメディアとして終わらせてはいけない。前述したような、双方向的な、自分が成長していけるものにしなければならない。
加えて、「手ぶらの知的生産」を可能ならしめているツールを有意義に使うことで、自分という資本の生産性を著しく高めることであろうか。(それでも、本文はローカルPCのワードで書いているが・)・)
もっと言えば、英語でブログを書いて、日本外に人にも読んでもらえるようになりたい。どういう内容であれば、関心を持ってもらえるのか、分からない。しかし、英語で書いていさえすれば、世界中の人たちとつながることができるのだから。
本書を読んだ結果、確実に私という一人の人間の仕事のスタイルや生き方は変わっていく気がする。そのように、人々の人生に持続的な影響力をもつ文章を書けるという意味で、梅田氏自身が私にとってのロールモデルとなっていることも、また確かだ。
■ 考える枠組み
|
|
「こっち」の世界
|
「あっち」の世界
|
|
大企業
|
|
|
|
ベンチャー
|
|
|
|
非営利団体
|
|
|
以上
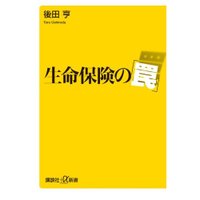
最近のコメント