M&Aの際に企業価値を算出する方法として、教科書で教えられるのが、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法。将来のキャッシュフローを予測し、それを一定の金利を用いて現在価値に割り引く手法だ。
当時出回っていた書籍には常にDCF法が書かれていたから、リップルウッドに就職してM&Aの現場に携わるようになって、これがほとんど使われていないことを知ったときは、驚いた。
実際にもっとも使われていたのが、EBITDA(≒営業キャッシュフローの代替指標)の4倍~6倍という業界平均の「マルチプル」(倍率)を用いて概算値を算出し、そこからバランスシートの細かい項目を時価評価などして引き算する方法だった。特に、買収ファンドにとっては、「いくらで買うか」もさることながら、「どうやって買うか(どれだけ買収資金を銀行から借りられるか)」ということも投資リターンに大きな影響を与える。また、とにかく「簡単に、客観的に」算定できることが必要だった。必ずしも「正確」な企業価値を算出することだけには躍起になっていなかった。
そして、それ以上に重要なのは、取引がおよそ相対で行われるものである以上、自分がいくら「この価格が真の価値だ!」と考えたところで、売り手にとって満足の行く価格でなければ、取引は一切成立しない、ということ。したがって、もっとも大きい要素は、相手の希望価格、すなわち「取引を成立するための値段」がいくらか、ということだった。
最後に、DCF法は、相手方に対して自分の価格を正当化するため、あるいは買収資金を貸してもらう銀行などに対しても企業価値を正当化するため、そして社内の投資委員会などに対して買収価格を正当化するためなど、参考となる補足材料として使った。その時も、ひとつの価格を見せるのではなく、たとえば「割引率が8%、10%、12%の場合」といったように、さまざまなシナリオで算出価格を見せていった。
結果として、「企業価値は100億円」という答えを出すのではなく、「100億円で買ったとしたら、20%の投資利回りが期待できる。80億円で買ったら、40%。100億円で買って30%近く狙うためには、収益率を3割以上改善する必要あり」といった風に、数字を使っていた。
そんな経験があるからか、生命保険のライフプランナーが営業の見積もりの際にもってくる「あなたに必要な保障額はこれくらいだ!」という数字も、さまざまな前提条件によって成り立つ、ひとつの参考値にすぎない、という風に考えている。前提条件を少し変えるだけで、数字はいく変わってくる。むしろ、数字は幅でとらえるものであり、他の要素を考慮して、あくまでも総合的にとらえるべきものである。
今日は午後に横浜にて保険セミナーを行ったのだが、そこで出た質問が、「私に必要な死亡保険金額はどのように考えればよいのですか?」というもの。そこでお答えしたのは、
① ライフプランのシミュレーションをやってみる(当社HP、または保険の営業マン)
② 皆が平均して死亡保険にいくらくらい入っているか、調べてみる(だいたい、平均3,200万円程度だったと記憶しています)
③ 業界で割安な保険会社から見積もりを取って、それと「自分がいくらくらいまで無理なく払えるかな~」という数字と比較する
という内容。
もったいぶる営業の方からもらうシミュレーションは、理論的に正しいのかもしれないが、結局前提条件を一つ変えるだけで数字は大きく変わってくるので、それも一つの参考値に過ぎない。そんな風に考えているので、当社の「必要保障額シミュレーター(←にバナーが張ってあります)」では、一回保障額を算出したあとに、「残された奥様にもっと質素に暮らしてもらう」とか「子どもを公立ではなく私立に行かせる」といった前提条件の変更を容易にできるようにしてみた。
数字の「正確さ」はその程度だと割り切って、それとともに、平均して自分と同じような人がどれくらい保険に入っているのか(≒業界平均)という数値を知って、あとは自分がいくらくらいまで保険料を無理なく払ってもいいと感じるか(こちらがわの言い値)を明確にして、その三つにトライアングルを総合的に考慮して、自分にふさわしい保障金額を決めるべきである。
金融のプロの現場でそうやってるのだから、皆さんも、それを真似ない理由はない。ぜひ、おためしください!

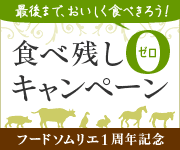
最近のコメント